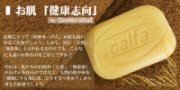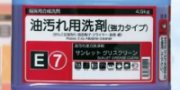次亜塩素酸の殺菌効果

上表は、殺菌力を持つと言われる各成分の殺菌効果の相対比較となっています。
ハイターやプールの消毒剤等で使用される次亜塩素酸ナトリウムの殺菌効果を100とした場合にそれぞれの殺菌効果を相対値で表しています。
次亜塩素酸(次亜塩素酸水)は、次亜塩素酸ナトリウムの10倍の殺菌効果を有しています。次亜塩素酸と同じレベルで殺菌効果を持つのは次亜臭素酸ですが、次亜臭素酸は次亜塩素酸以上に不安定な成分であり、また、生成価格も高額となるため、除菌製品としてはあまり商品化されていません。一部、塩素耐性菌用の業務用除菌剤として製品化されているものもあります。
クロラミン(結合塩素)は次亜塩素酸ナトリウムと比較すると殺菌効果が1/10、次亜塩素酸と比較すると1/100となります。次亜塩素酸と窒素が結合するとクロラミン(結合塩素)となります。俗にいう塩素臭はクロラミン臭とも言いますが、次亜塩素酸が菌や汚れなどの有機物とぶつかって除菌した後の除菌臭とも言えます。
一方、ブロラミン(結合臭素)は、クロラミンと異なり、窒素と結合しても殺菌効果が落ちない成分です。塩素と臭素でこんなにも違いがあるのが面白いですね。
下表は次亜塩素酸水での一般的な殺菌効果の試験結果です。次亜塩素酸水そのものの殺菌力の目安としてご覧いただければと思います。
残留塩素濃度10ppmと20ppmでの測定となっていますが、一般家庭と試験環境との環境差異がありますので、ご家庭や施設等でお使いになる場合は、残留塩素濃度を100ppm〜200ppm目安でご利用になってください。


実物検体の採取保管が難しいウィルスもあるため、この手の試験には「類似ウィルス」を用いて試験されることがあります。例えば、「ノロウィルス」への効果試験では、「ネコカリシウィルス」を用いるのは有名な話です。
次亜塩素酸の酸化によるウィルス不活化のメカニズムは、基本的にウィルスが細胞に吸着するための接触子(スパイク或いはエンベロープタンパク質と言います)を破壊するものなので、インフルエンザであろうと、ノロウィルスであろうと、肝炎ウィルスであろうと、基本的に共通の不活化メカニズムであると言われています。